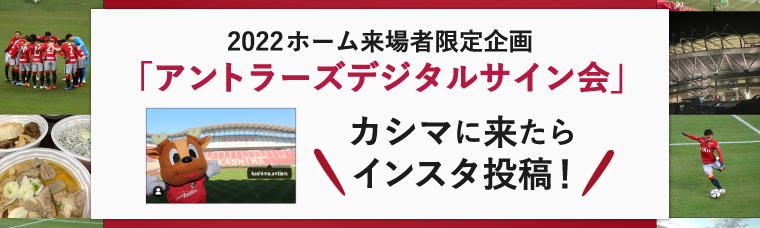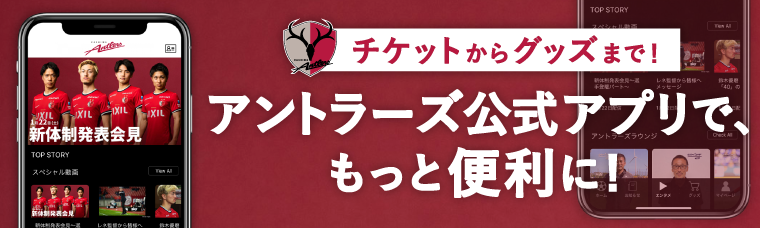PICK UP PLAYER

樋口雄太が本格的にボールを蹴り始めたのは、6歳のころだった。きっかけは、2002年の日韓W杯。「自分もあの舞台で活躍したい」と、日本代表を夢見たことだった。
小学生になると、地元の三根FCへ加入。小学3年生で鳥栖U-12のセレクションを受けた。ずっと対戦相手として試合をしながら、「強いな」「ここに入りたいな」と思っていた憧れのチームだった。
セレクションで合格した樋口は、そこから鳥栖のアカデミーで育った。体格が大きい方ではなかったため、悔しい思いを味わったことも多かったというが、「必ずトップチームに上がる」という強い信念のもと、日々の鍛錬で技術を高めていった。
「ユースのときは、技術面でいえばキックにとても自信があった。でもそれ以上に、自分の強みはメンタルだとも考えていた。目標に向かってやり続ける。その気持ちは誰にも負けないと思っていた」
努力した分、己の成長も実感した。だから、プロでやっていく自信も、もちろんあった。

しかし、現実は厳しかった。「トップチームには昇格できない」。通告された瞬間、ショックが大きすぎて、いま思い返してみても、記憶からスッポリと抜け落ちている。トップチームでプレーすることを目指して練習を続けた10年間。「なぜ?」という思いだけが、頭の中をぐるぐると渦巻いた。
だが、それでも彼がその足を止めることはなかった。トップチーム昇格が叶わなかった時点で、さまざまな選択肢があったものの、他の地域でのプレーではなく、地元九州の強豪・鹿屋体育大学への進学を決めた。すべては幼き頃からの目標を叶えるため。覚悟が必要な決断だった。
「トップに上がれないと言われてすぐは、反骨心から『他のチームに行って見返してやろう』と思った。でも、やはり自分の生まれ育った九州の大学に通って、4年後にまた鳥栖に戻ろうという気持ちに変わっていった」
進学した鹿屋体育大学では、フットボールの技術向上はもちろん、体育大学ならではの身体に関する知識を身につけ、人としても多くのことを学んだ。「応援してくださる方々がいるから、自分たちはプレーできる」。心身ともに一段と成熟し、月日を重ねるごとに、自然と周囲からの評価も高まっていった。
そして、プロの世界へ足を踏み入れるタイミングで、鳥栖からのオファーが届いた。そこからの飛躍は、広く知られるとおりだ。1年目は出場機会に恵まれなかったが、2年目にレギュラーポジションを確保。3年目には、リーグ戦6得点、6アシストを記録し、大きな注目を浴びた。幼い頃から憧れたチームで10番を背負い、戦える喜び。自分の心の中に、その気持ちは間違いなく存在していた。

しかし、プロ4年目を迎えた2022シーズン。自身の大きな夢を叶えるために、アントラーズへの移籍を決断した。
「本当に最後の最後まで悩んだ。ただ、自分のなかには『日本代表になる』という目標があった。そのために、アントラーズという新しい環境に身を置き、さらなる成長を目指す道を選んだ」
自身の夢のため、成長のため、新たな環境を選択した。

まだ加入して日は浅いが、ここまでの彼の活躍を見る限り、その決断は間違っていなかったと思える。「合流初日から驚いた」という強度の高い練習は、自身のプレーの幅を大きく広げ、さらなる成長をもたらした。
「アントラーズに加入して自分のプレーの幅は広がったと思う。90分間を通して、いろいろなエリアに顔を出し、積極的に攻守にかかわるという部分に成長を感じる。チーム全体を助ける動き、仲間のために走るといったプレーは、これまでの僕に足りなかった要素。アントラーズに加入してから、より伸ばせた部分かなと思う」
幾多もの得点を演出してきた正確なキックに、的確な判断、戦術眼、運動量。さらに献身性と守備の強度まで加わった。リーグ戦ではここまで全試合に先発出場。いまやチームの心臓として、文字通り欠かせない存在となった。

そして、今節。樋口雄太はアントラーズの一員として、初めて古巣と対戦する。アカデミーからお世話になった鳥栖への感謝は、今もこれからも、決して忘れることはない。だが、今はアントラーズの勝利のために献身を尽くすことしか、頭の中にはない。
「この試合をすごく楽しみにしていた。鳥栖のことは今でも気にしているし、好きなチームの一つ。ただ、だからこそ、アントラーズの勝利に貢献して、成長した姿を見せたい」

誠実で静かな口調からは、古巣への心からの感謝とアントラーズのために献身を尽くす決意が伝わってきた。彼はきっとこの先も、足を止めることはない。覚悟を持って選択した道を、迷うことなく突き進むだけだ。
「鳥栖で経験したこと、積み上げてきたことは、今に活きているし、アントラーズで活きていると感じる。恩返しではないけれど、鳥栖の時よりも成長した姿を見せたいし、それをピッチで証明したいと思う。勝ちにいきたい」
すべては勝利のために。アントラーズの背番号14、樋口雄太は走り続ける。